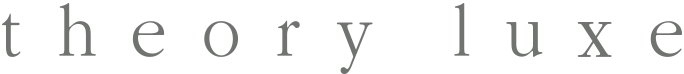大きな地図を描く
ハーレムの自宅でディナーをふるまうときも、コートジボワールのホテルでアーティスト・レジデンシーを主催するときも。シェフ、ロゼ・トラオレにとってもっとも大切な素材は、「自由な探求」。
ロゼ・トラオレは、文字どおり「世界各国の料理」を生きるシェフだ。拠点はニューヨークとコートジボワール。
アメリカ、フランス、西アフリカにまたがるルーツと旅の記憶が、皿の上に静かに息づく。由緒正しいフランス料理の技術を背景に、ファッションと食を横断する体験型イベントを手がけてきた。ロゼの料理は、風まかせの帆のように、どこへ連れていかれるのかわからない軽やかさをまとっている。あるときは、フランスの伝統的技法「コンカッセ」で湯むきされたトマトと、ポーチドしたニューイングランド産のロブスターを組み合わせて。あるときは、しっかりと焼きつけたシャントレル茸にバターを絡め、噛みごたえのある黒米とともに供する。ニューヨークのファーマーズマーケットで手に入れたズッキーニが主役になる日も。ピクルス、炭焼き、コンフィ。三つの異なる調理法で仕上げられ、地元のスズキとともに初夏の皿を彩る。記憶と技術に支えられた遊び心。ルーツも文化も超えて、人は「味覚」でつながれる。そんな静かなメッセージが料理から立ち上がる。
ある朝、ハーレムの自宅で、ロゼはゆったりと語ってくれた。シェフとして歩んできた道のり、そして自身のホテルを立ち上げたことが、アフリカ系ディアスポラのアーティストたちと深くつながるための大きな一歩だったということ。
コーシャ・ウィルソン(KW):育った場所、そして「料理」と出会ったきっかけについて教えてください。
ロゼ・トラオレ(RT):生まれはワシントンD.C.で、育ちはD.C.とコートジボワール、パリを行き来してました。父は漁師で、何ヶ月も海に出ては、3〜6ヶ月ぶりに帰ってくる。そうすると母が、父の子どもの頃の好物をつくるんです。たとえば、ピーナッツソースとポワソン・ブレゼ(魚の煮込み)、それにプランテン(アフリカ料理によく使われる調理用バナナ)など。いま思えば、父にとってそれは「ふるさとの味」だったし、同時に私たちに文化を伝えたいという思いもあったんだと思います。そういう経験が、料理への愛を育ててくれたんですね。でも、実際に料理の道を意識したのは、高校卒業後に進路を考えはじめた頃です。それまで暮らしてきた場所の料理について、もっと深く知りたいと思った。そうしてル・コルドン・ブルーで学んだあと、ファインダイニングの世界と、ファッションの世界。両方に惹かれている自分に気づいたんです。そこから、すべてが動き出しました。
KW:料理学校を卒業してから、いくつもの一流レストランで働いていますよね。そこでの経験は、どんなものでしたか?
RT:子どもの頃のD.C.での思い出をもう一度たどりたくて、いちばん評価の高いレストランを調べたんです。当時は、エリック・ジーボルドがシェフを務める〈CityZen〉がそうでした。そこで働きながら、休日にはニューヨークへ行って、モデルエージェンシーを訪ねたりしていました。そのコミュニティのなかで、ニューヨークの飲食業界を見渡して、いろんなシェフと知り合っていったんです。やがて、ファッションの撮影現場向けのケータリングを担当するようになり、「体験」をどうキュレーションできるかを考えるようになりました。そういう物語性のある仕事に惹かれたんですね。それで、料理とファッションを意味のあるかたちで組み合わせていくようなシェフになりたいと思うようになりました。10年前のことです。当時はまだこういうスタイルは珍しかったけれど、いまではこの分野も大きく広がっています。もともと「つくること」が好きだったし、レストランの仕事も楽しかったけれど、ふたつの世界を掛け合わせて、新しい客層に表現できることに、とてもワクワクしました。
KW:料理とファッション、どちらかに関わっている人はいても、両方の世界をプロとして行き来している人はあまりいませんよね。ふたつの世界に共通するものって、何でしょう?
RT:完璧さへの執着と、ディテールへのこだわり。どちらの世界にもそれがあります。それだけで、私にとっては十分に満たされる感覚があるんです。でもそこにもうひとつ、「アート」という要素も加えたくなった。それで、経営するコートジボワールのホテルでは、アーティスト・レジデンス・プログラムも始めました。いまの私は、ファッションの現場で料理をするだけでなく、現代を代表するようなアーティストたち。画家、音楽家たちとつながりながら、彼らが創作できる場をつくっているんです。そういう関係性を築いていくのが、最近のいちばんの情熱ですね。
KW:アフリカ系アメリカ人のアーティストたちとつながってホテルに招くというのは、どんな意図ですか?
RT:アフリカに興味を持っているアーティストって、本当に多いんです。でも、実際に訪れる機会がなかった人たちばかり。だったら自分が場を用意しよう、と思ったんです。故郷の大地に足を運び、そこでものをつくる。その体験を共有したかった。継続すること、成長し続けることって、本当に難しい。でもだからこそ、じっくり腰を据えて制作できる場をつくりたかった。もうひとつは、純粋に、アーティスト同士の交流が好きなんです。昔の写真で、マイルス・デイヴィスとジョン・コルトレーンが一緒に演奏している姿があるんですけど。そういうふうに響きあいながら何かが生まれていく瞬間って、見ているだけで胸が熱くなる。自分自身も、このコミュニティに入っていって、関係を深めていくことで、本当に豊かな時間を過ごしてきました。料理と同じです。アートが人をつなげてくれる。でもそれ以上に、そこに宿るエネルギーや、交差する空気そのものが、忘れられない体験をつくってくれるんです。